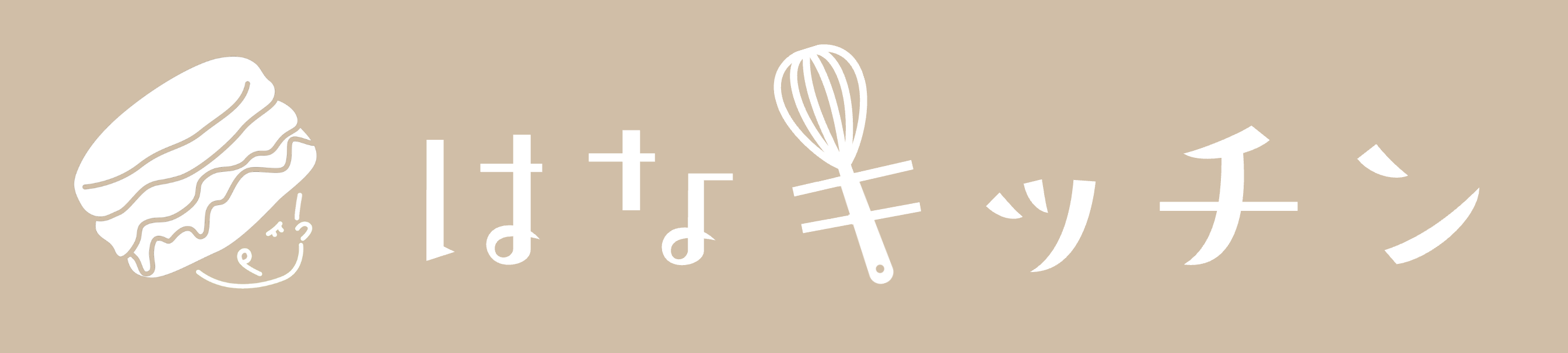ブリティッシュベイクオフでは毎回、その回のテーマに関連した食べ物の歴史を紹介するミニコーナーがあります。
司会者のスーやメルが歴史家や専門家と一緒に、知られざる食文化の物語を探訪します。
今回はシーズン5の中で紹介された歴史コーナーをまとめてご紹介します。
Episode 2: アイスクリームについて

イタリア移民がもたらしたジェラート文化
19世紀初頭、ナポレオン戦争後の多くのイタリア人がイギリスに移住し、マンチェスターのアンコーツ地区などに定住しました。
彼らが持ち込んだのが、故郷の名物ジェラートでした。
食物史家のA・エドワーズによると、当時のアイスクリーム製法は極めてシンプルで、「温めた牛乳に砂糖を溶かし、木の器に入れて手でかき混ぜる」というものでした。
長屋の寒い地下室は天然の冷蔵庫として理想的な環境を提供していたのです。
衛生問題を生んだ「ペニーリック」
街頭でのアイス販売は「ペニーリック」という方式で行われていました。
これは1ペニーでアイスを購入し、客が最後の一滴まで舐め尽くした(=リック)器を使い回すというものでした。
経済的には合理的でしたが、衛生面では深刻な問題を抱えており、疫病の蔓延により1899年に禁止されることになります。
アイスコーンの誕生
この危機を救ったのが、アンコーツのアントニオという人物でした。
彼はベルギーで既に実用化されていた食べられる器からヒントを得て、地下室でアイスコーンを開発しました。
初期のコーンは底に穴が開いていましたが、すぐに食べ切ることを前提としていたため問題はありませんでした。
小麦粉、水、糖蜜を原料とし、鋳鉄製のパンで両面を焼いた生地を、椅子の脚などから作った木型に巻き付けて成形。
冷めて固くなれば、革新的なアイス用コーンの完成でした。
アイスクリームコーンの発明については諸説ありますが、1904年のセントルイス万博で普及したという説が一般的です。
しかし、イギリスでのイタリア系移民による独自の発展も重要な歴史の一部です。

Episode 3: スパイスについて

スパイス貿易の変革
長年にわたってオランダやポルトガルが独占していたスパイス貿易に、1600年にエリザベス1世の特許状により設立された東インド会社が参入しました。
これにより、かつては高級品だったスパイスが、次第に庶民の日常生活にも浸透していきました。
ウィッグパンの誕生
スパイスの普及とともに生まれたのが「ウィッグ」と呼ばれるスパイス入りのパンでした。
食物史家アニー・グレイの解説によると、1700年代のE.C.スミスの料理書に記載されたレシピでは、メース、ナツメグ、クローブ、そしてキャラウェイシードが使用されていました。
このウィッグパンは、イギリス人が愛する菓子パンやケーキの元祖とされています。
当時の日記には「ビールと一緒に食した」という記録も残されています。

Episode 4: プディングについて

ペイントンの巨大プディング
美しい海岸沿いの町ペイントンでは、13世紀から巨大なプディングを作る伝統が続いています。
1859年の鉄道開通記念では、なんと1.5トンものピラミッド状プディングが制作されました。
スポッテッドディックと贅沢な材料
伝統的なスポッテッドディック(干しブドウ入りプディング)の材料には、当時としては非常に高価だった干しブドウ、レモン、ナツメグなどが使われていました。
プディングは庶民にとって特別なごちそうでした。
1万8千人の暴動
歴史家ポール・クリーブ博士の証言によると、真夏の8月にプディングの分配を待つ群衆が興奮のあまり暴徒化したという記録が残されています。
1万8千人という規模は、当時のプディングがいかに価値ある食べ物だったかを物語っています。

Episode 5: ウェディングケーキについて

古代の結婚式の風習
現代では定番のケーキカットですが、古くは新郎が幸運を祈って新婦の頭上でケーキを割るという儀式でした。
また、パイとビスケットの山越しにキスをする伝統もありました。
17世紀の「花嫁のパイ」
食物史家アイヴァン・デイによると、17世紀の結婚式では子宝を願う媚薬効果があるとされる食材を使った「花嫁のパイ」が定番でした。
羊の精巣、牛のほほ肉、ひづめ、そしてルネサンス期最強の媚薬とされたアーティチョークなどが使用されていました。
ブーケトスの原型
特に興味深いのは、パイの中にガラスの指輪を隠し、それを見つけた人が次に結婚するという風習です。
これは現代のブーケトスの原型とも言える伝統でした。

Episode 6: デンマークのケーキについて

プロイセン統治下の文化的抵抗
1864年のユトランド半島へのプロイセン侵攻後、南ユトランド地方ではデンマーク語さえ禁止される厳しい統治が行われました。
住民のソフィ・エゲルによると、国民性を表現する手段として秘密の組合が結成され、集会が開かれました。
ケーキによる静かな抵抗
酒類が禁止されていたため、代わりに持ち寄られたのがケーキでした。
ここで味や美しさが競われ、実質的な「ベイクオフ」が開催されていたのです。
このケーキテーブルと呼ばれる慣習は現在も続いています。
現代のケーキマラソン
テーブルにずらりと並んだケーキ。
シェフのトリーネ・ハーネマンによるとこれは「Sønderjysk kaffebord」(=ケーキを食べ続けるという意味)で、3〜4時間もの間ケーキを食べ続けます。
酵母部門、ドライ部門、クリーム部門を経てゴールに至る間、参加者は5〜7杯のコーヒーとともに様々なケーキを食べるのだそうです。

Episode 7: コーニッシュ・パスティについて

鉱山労働者の海外派遣
19世紀初頭、コーンウォールは世界有数のスズ産地でした。
1825年、優れた採掘技術を持つ60人の労働者が、1500トンの設備とともにメキシコの銀山に招かれました。
14ヶ月の長旅を経て、パチュカとレアルデルモンテの銀山に到着した彼らは、現地の労働者たちと文化交流を深めました。
メキシコ風「パステ」の誕生
鉱山コンサルタントのスティーブン・レイによると、メキシコの労働者たちはコーニッシュ・パスティの実用性に魅力を感じました。
簡単に大量生産でき、職場に持参できる理想的な食事だったからです。
現地での食材調達の制約から、メキシコ版の「パステ」は独自の進化を遂げました。
ベイカーのマリオン・サイモンズの説明では、イモ、ニラネギ、唐辛子、牛肉、パセリなどが使用され、オリジナルより小ぶりで具がたっぷり、そして非常に辛いのが特徴です。
190年続く絆
現在でも両国の労働者の子孫が定期的に集まり、この食文化の絆を祝っています。
ただし、メキシコ版の辛さは現代のイギリス人には強烈で、「涙が出るほど辛い」という感想も聞かれます。

Episode 9: バウムクーヘンについて

木組みの街ザルツヴェーデル
全長3000キロに及ぶ「木組みの家街道」沿いに位置するザルツヴェーデルは、「バウムクーヘンの街」として知られています。
「木のケーキ」を意味するバウムクーヘンは、ドイツのベイカーにとって究極の試練とされる極めて難易度の高いお菓子です。
1807年から続く伝統レシピ
ザルツヴェーデルの老舗店では、1807年から変わらぬレシピが受け継がれています。
小麦粉、バター、砂糖、そして1本につき約40個もの卵を使用する贅沢な配合です。
本編に登場したのシヒトトルテとは異なり、回転する串に生地をかけながら焼き上げる特殊な技法が用いられます。
熟練職人の技
15歳からバウムクーヘンを焼き続けているベイカー長のマイク・ズスケは、1日約20本を生産しています。
生地を均等にかける技術、適切な焼き加減の見極め、そして美しい年輪模様を作り出す技術は、まさに職人技。
完成したバウムクーヘンは24時間冷ました後、フォンダンまたはチョコレートでコーティングされ、11キロにもなる巨大な菓子として仕上げられます。
バウムクーヘンは1919年に神戸でドイツ人カール・ユーハイムによって日本に紹介され、現在では日本の方がドイツより消費量が多いとされています。

まとめ
今回はブリティッシュ・ベイクオフ シーズン5の歴史コーナーをご紹介しました。
日本にいるとなかなか知ることが出来ない、洋菓子や料理の歴史や食文化を紹介してくれるコーナーもブリティッシュ・ベイクオフの魅力の1つです。
今回でブリティッシュ・ベイクオフ シーズン5の投稿は終了です。
秋ごろから、ブリティッシュ・ベイクオフ シーズン1をご紹介する予定です。